COLUMN
AGV(無人搬送車)とは?導入するメリット・デメリットやAMRとの違いを解説

新型コロナウィルスの流行や、IT業界の目覚ましい進化によって多忙を極めているのが物流業界です。
その物流業界において、大活躍しているのがAGV(無人搬送車)です。
今回はAGVについて、導入するメリット・デメリットやAMRとの違いを解説します。
AGV(無人搬送車)とは
とは-1024x576.png)
AGV(無人搬送車)とは、Automatic Guided Vehicleの略語で、物流倉庫内の運搬作業を人に代わって行うロボットのことをいいます。モデルによっては、荷物を上に載せて運ぶだけでなく、けん引することも可能です。人間が操作を行う必要がなく、予め設定された通路を通って荷物を搬送します。
AGV自体は近年開発されたものではなく、90年代から存在しており、工場の製造ラインをはじめとした、さまざまな場所で使用されていました。
そのAGVに、最新のAI技術を搭載したものが開発されたことによって性能が格段に向上したため、今日の物流現場における普及が進んでいます。
AGV(無人搬送車)とAMRの違い
AMR(自律搬送)とは、Autonomous Mobile Robotの略語で、自律走行搬送を行うAGVのことをいいます。AGVとAMRとの違いは、走行するためのガイドラインの有無と導入コストです。
AGVは、磁気テープやランドマーク式といった、決められたルートの上を走行するのに対して、AMRは走行するためのガイドラインを必要とすることなく、周囲の状況に応じて適切なルートを自ら判断して搬送します。そのため、AGVはガイドラインの導入コストがかかりますが、AMRはガイドラインのコストがかかりません。
AGV(無人搬送車)の代表的な搬送方法
の代表的な搬送方法-1024x576.png)
一口にAGVといっても、モデルによって搬送方法はさまざまです。ここからは、AGVの代表的な搬送方法を解説していきます。導入の際は、現場に適した搬送方法のAGVを選ぶことが大切です。
けん引型
けん引型は、荷物を上に載せるのではなく、後ろにカゴやパレットといった台車を連結して引っ張る(けん引)タイプのものになります。荷物の量に合わせて台車を複数連結することもできるので、一度に大量の荷物を搬送することも可能です。
モデルの中には、数百キロ〜数トンまでけん引できるものもあるので、荷量に合わせたAGVを選ぶことができます。
低床型
低床型のAGVは、台車やパレットの下に入り込み、リフトのように持ち上げて搬送するタイプになります。低床型のAGV自体がリフトのように荷物を上下させられるので、人が荷物を降ろす必要がないのが特徴です。
搬送する台車の車輪の有無も関係なく搬送できるため、けん引装置をつけることが難しい台車を搬送することもできます。
軽量のモデルから約1tまでのものを搬送できるモデルもあり、これまで人がフォークリフトを利用して搬送していた作業を、自動化することが可能です。
自動移載型
AGVにコンベアがついているタイプです。地上側にあるコンベア間の搬送自動化に役立ちます。
これまで発生していたヒューマンエラーや、24時間の稼働もできるため、物流コストの大幅な減少実現が可能です。
台車型
台車型とは、手押しの台車型のような形をしているタイプです。台車の上に直接荷物を載せて搬送します。
これまで人が台車を押して搬送していた作業の自動化が可能です。作業員の負担軽減やヒューマンエラー防止の効果が期待できます。
AGV(無人搬送車)の代表的な走行方法
の代表的な走行方法-1-1024x576.png)
続いて、AGVの代表的な走行方法を解説していきます。AGVの走行方法によって、導入コストも異なるので、予算や現場の状態に適しているかどうか、しっかりと判断するようにしましょう。
ランドマーク式
ランドマーク式は、地面に貼られた二次元コードの情報をAGVがカメラで読み込み、指示を受けながら走行します。所用部分にのみランドマークを貼ることで、簡単にルート作成ができるのが特徴です。
また、一般的な走行方法ではコストがかかるルートの追加や変更など、アプリ上で指示の上書きをすることもできます。
磁気誘導・ライントレース式
磁気誘導・ライントレース式は、走行させたいルートの床に磁気テープを張り巡らし、その磁気をAGVが読み取りセンサーで読み込み走行します。磁気センサーの読み取りが正確なため、直進や停止など動作精度が高いのが特徴です。
走行ルートに貼るものとしては、主に磁気テープが使用されますが、電磁誘導ケー反射テープを使用する方法もあります。
他にも、埋め込み式と比較すると、設置コストが抑えられるため、日本国内で広く普及しています。
SLAM式(AMR)
SLAM式とは、Simultaneous Localization and Mapping(自己位置の特定と地図作成を同時に行う)の略語です。事前に経路を床に設置する必要がなく、AGV自体が自分の位置を把握しながら走行します。正確には、前述したAMRに分類されますが、AGVとして扱われることもあります。
現場や棚の場所が変わりやすい・床に経路指示のテープを貼ることができない場所で、導入されることが多い走行方式です。
AGV(無人搬送車)の導入メリット
の導入メリット-1024x576.png)
今日の物流現場で大活躍している、AGVの導入メリットを解説していきます。
生産性
従来は人が行っていた単純作業をAGVを導入して自動化することによって、人による作業スピードのムラがなくなり、主要部分に人員を充てることもできるため、生産性が向上します。また、長期的な人材不足の解消も実現可能です。
他にも、人がいない時間帯にも搬送物の配置転換を行うことで最適化し、稼働時間を効率よくすることも出来ます。
ミスの軽減
AGVはロボットなため、機械トラブルや操作ミスなどがない限り、一度指示した内容を間違えることがありません。人では実現できない作業の正確さが特徴なため、ヒューマンエラーの軽減を実現することができます。
作業員の負担軽減
商品の仕分けや指示書の受け取り、ピッキング作業など、いずれか一つでもAGVが作業を担うことで、作業員の負担軽減が可能です。
更に、AGVに搭載されたセンサーによって、自ら障害物を避けたルートを走行するため、接触事故の防止といった安全性の向上もメリットとして挙げられるので、大幅に作業員の労働環境が整います。
コスト削減
人件費や新人教育にかかる費用、作業服をはじめとした備品に快適な作業環境維持費など、さまざまなコスト削減が実現可能です。AGV自体も常に進化をし続けているものなので、今後は電力効率の向上したAGVが登場し、更なるコスト削減が実現できると期待されています。
AGV(無人搬送車)の導入デメリット
の導入デメリット-1024x576.png)
AGVの導入デメリットは、コストです。
AGVを導入するにあたって、AGVの本体購入費用・ガイドラインの設置費用・保守メンテナンス費用・システムの連携費用などがかかります。導入するAGVの走行方法や搬送方法といった細かな条件によって導入費用は異なるので、予算に見合ったAGVを選ぶことが重要です。
AGVは初期投資費用がかかりますが、長期的に見ればメリットが勝ってくるので、ある程度の投資が必要になります。
システムと連携させることで更なる効率化が可能
AGV自体だけでも非常に有能ですが、更に倉庫内の作業効率を向上させることを目的として、他のシステムとの連携機能が重要視されています。一般的には、搬送を自動化させたとしても、荷物を載せるための人が必要です。
しかし、荷物を載せたり降ろしたりする作業もシステム化し、そのシステムとAGVが連携することができれば、AGVのみを使用した場合よりも、更なるコスト削減や生産性の向上を実現できます。
AGVは、どのシステムとどのように連携させるか、倉庫の全体を視野に業務設計することが重要です。
AGV(無人搬送車)の導入検討ポイント
優れた性能を持つAGVですが、導入をする際に何を重視すればよいのかわからない人もいるでしょう。ここからは、AGVの導入検討ポイントを解説していきます。
コストパフォーマンス
AGVの導入をするにあたって、どれぐらいのコストパフォーマンスが得られるのかは重要です。AGVを導入することで、生産性の向上や作業員の負担軽減など、さまざまなメリットを得ることができますが、AGVは導入して終わりではありません。
ロボットなので維持管理コストもかかります。アップデートがあった場合の対応や、他のシステムとの連携機能など、導入した後にも継続してかかる費用を考慮する必要があります。
そのため、導入した際に、費用と効果のバランスがとれるかどうか、費用よりも効果の方が上回るかどうか、しっかりと検討するようにしましょう。
現場に適した搬送・走行方法であるかどうか
最新モデルのAGVであっても、現場に適していなければ、AGVの機能を上手く活かすことができません。AGVによって搬送方法や走行方法はさまざまです。導入検討しているAGVが現場に適した搬送・走行方法をするものかどうか、確認するようにしてください。
実働しているAGV(無人搬送機)例
日本国内でも広く普及しているAGVですが、馴染みのない人にとっては、いまいちイメージが掴めないかもしれません。そこで、実際にどのようなAGVが実稼働しているのか、いくつか例を紹介していきます。
t-Sort
t-Sortは、次世代型のロボットソーターで、決められた場所に商品を運搬・オートメーションで仕分けを行います。t-Sortの特徴は、最大30kgまでの荷物に対応しており、5〜10分程度の充電で最大4時間連続稼働できる、一般的なソーターよりも省スペースであることです。
作業の効率化向上に大きく貢献するため、海外では5,000台以上の導入実績を誇ります。
CarriRo
CarriRoは台車タイプのAGVになります。種類によって、人が力を使わずに運搬できるドライブモードや床に貼られたガイドラインを認識して無人運搬する自律移動モードなど、さまざまな機能が搭載されています。
オプションの種類も豊富で、パレットタイプの台車やけん引用アタッチメントなどを使用すれば、性能が高まる上、数時間で走行ルートの設定もできるため、即日の稼働が可能です。
まとめ

AGVは、物流現場において優れた効果を発揮します。しかし、やみくもに利用しても、期待した効果を得ることはできません。導入する現場に適しているかどうか、しっかりと確認してから導入するようにしましょう。
物流現場の自動化をどのように進めていけばよいのかわからない場合は、ロジテックエンジニアリングサービスがおすすめです。
AGVの導入を検討している場合は、弊社のロジテックエンジニアリングサービスの利用もご検討ください。



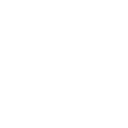 メールフォーム
メールフォーム