COLUMN
物流のKPI(物流管理指標)とは?計算方法や設定するメリットなどを解説!
とは?計算方法や設定するメリットなどを解説!-1024x576.png)
世界中を大混乱に陥れたコロナ感染症を経て、ECサイトでの買い物が普及している今日の物流業界では、効率的な業務運営やコスト削減が非常に重要視されています。
そのため、物流のパフォーマンスを数値で捉え、改善するために用いられるのが「物流KPI(物流管理指標)」です。KPIを正しく設定することで、物流業務全体の改善を図り、競争力を高めることが可能になります。
本記事では、物流KPIの具体的な種類や計算方法、導入するメリット、さらなる効果設定方法について詳しく解説していきます。物流の効率化を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
物流KPI(物流管理指数)とは
とは-1024x576.png)
物流KPI(Key Performance Indicator)は、物流業務のパフォーマンスを定量的に測定するための指標です。物流業務における商品の受注、倉庫での保管、出荷、配送、在庫管理など、複数の工程や業務を効率化・評価し、課題を見つけて明確にすることができます。
例えば、出荷ミス率が高い場合、物流KPIを活用してその原因を特定し、適切な対策を講じることで、出荷業務の改善を心がけることが可能です。また、輸送コストが高い場合は、配送経路や使用する輸送手段の最適化の検討が必要なことがわかります。
このように、物流KPIは企業の物流活動全体を定量的に把握し、戦略的な改善を行うために重要な役割を担っています。物流KPIを活用することで、企業は物流プロセスの効率化を目指し、顧客満足度を高めることができるのです。
物流KPIの指数と計算方法

物流におけるKPIには、さまざまな種類があり、それぞれのKPIは特定の業務領域に焦点を当てているのが特徴です。物流業界では、主に「コスト・生産性」、「物流・配送条件」、「品質・サービス」の3つを参考にしてKPIを設定します。
以下より、それぞれのKPIの詳細と計算方法について、具体例を挙げながら解説していきます。
コスト・生産性
物流業務に関しては、コスト削減と生産性向上が重要な課題です。コストと生産性に関連するKPIを正しく設定することで、効率的な運用が実現可能です。
| 指標 | 計算方法 |
| 積載率 | 積載数量÷積載可能数量 |
| 実車率 | 実車距離(km)÷走行距離(km) |
| 実働率 | 働日数÷営業日数 |
| 保管効率 | 保管間口数÷総間口数 |
| 倉庫内作業のひとり当たり生産性 | 処理数÷投入人時 |
| 誤出荷率 | 誤出荷発生件数÷出荷指示数 |
| 棚卸差異率 | 棚卸差異÷棚卸資産総数 |
| 汚破損率 | 汚破損発生件数÷出荷指示数 |
| 遅延・時間指定違反率 | 遅延・時間指定違反発生件数÷出荷指示数 |
| 数量あたり物流コスト | 物流コスト÷出荷数量 |
| 日次収支(物流センター・トラック) | 1日あたりの収入-1日あたりのコスト |
物流・配送条件
物流・配送に関連するKPIは、納期や配送精度を中心に測定されます。これらのKPIを適切に管理することで、顧客満足度や物流業務性を向上させることが可能です。
また、物流・配送条件に関するKIPは、計算をして算出するものではなく、数を明確に認識することが多いのも特徴です。
| 指標(計算方法) | 内容 |
| 配送頻度(配送回数÷営業日数) | 顧客や納品先ごとの配送回数を追跡する指標です。配送頻度を上手く調整することで、車両の稼働効率を最適化し、倉庫内作業の効率向上が期待できます。 |
| 出荷ロット | 出荷数量や重量のことを指しており、顧客や納品先ごとに計測することで、輸送効率や倉庫内の作業効率を向上させることができます。 |
| 納品先待機時間 | 納品先に到着後、待機した時間の平均を計測した指標です。定時に到着しても待機時間が長い場合には、対策を講じる必要があると考えられます。 |
| 納品付帯作業時間 | 納品時に発生する付帯作業(開梱、棚入れ、検品など)にかかる時間の平均を示す指標です。契約外の作業が頻繁に発生している場合、契約内容の見直しや対応策の検討が必要なことがわかります。 |
| 納品付帯作業実施率(付帯作業実施回数÷納品回数) | 納品回数に対して、どの程度付帯作業が実施されたかを示す指標です。納品付帯作業時間と併せて分析することで、付帯作業の全体的な状況を把握できます。 |
| 出荷指示遅延件数 | 納品期日を過ぎてから出荷指示が出された件数を測定する指標です。この指標は、輸送の遅延を減らし、納期遵守の改善に役立ちます。 |
品質・サービス
品質やサービスは、顧客の満足度に直結する重要な要素です。品質に関連するKPIを正しく管理することで、顧客クレームの削減やリピート率の向上が期待できます。
| 指標 | 計算方法 |
| 棚卸差異率 | 棚卸差異÷棚卸資産総数 |
| 誤出荷率 | 誤出荷発生件数÷出荷指示数 |
| 遅延・時間指定違反率 | 遅延・時間指定違反発生件数÷出荷指示数 |
| クレーム発生率 | クレーム発生件数÷出荷指示数 |
| 汚破損率 | 汚破損発生件数÷出荷指示数 |
物流KPIを設定するメリット

物流KPIを設定することで、物流業務に関するさまざまな課題を数値化し、効率的に改善策を打ち立てることができます。物流KPIの設定をすることで期待できるメリットを見ていきましょう。
課題を可視化
物流業務は、全体のプロセスを可視化するのが難しいとされているため、物流KPIを設定することにより、物流業務のどの部分がボトルネックとなっているか、またどの業務が効率的に行われているかを明確に把握することができます。
これにより、問題の原因を的確に特定し、解決策を見出すことが可能です。例えば、納期遵守率が低い場合、その原因が倉庫内の作業遅延にあるのか、配送計画の不備にあるのかを見極めることができるため、具体的な改善策を迅速に講じることができます。
目標の共通化
物流KPIを設定することは、全社的に共通の目標を持つことを可能にします。漠然としたものではなく、具体的に「配送遅延率を5%以下に抑える」という目標を掲げることで、物流部門だけでなく、営業部門や顧客対応部門など関係者全員との連携が強化されます。
部門を超えた共通の目標を持つことで、社内全体での一体感が生まれ、業務の効率化が図られます。
評価の公平性
物流KPIは、従業員や部門のパフォーマンスを客観的に評価するための基準としても機能します。例えば、出荷ミス率が低い従業員は高く評価され、配送遅延を防いだチームもその成果を評価されるのがベストです。
そのため、数値に基づいた公平な評価は、従業員のモチベーション向上に繋がります。また、努力が公平に評価されることで、人間関係の改善や離職率の低下など、物流業界が抱える課題解消効果が期待できるでしょう。
物流KPIの導入手順

KPIを導入する際には、明確な手順に従って段階的に実行することが重要です。以下に、KPI導入のプロセスを段階的に説明します。
現状の分析・把握と基盤整備
まずは、現場でのヒアリングや既存のデータが入手できるかどうかを明確にします。データの入手が可能な場合は、現状の物流プロセスを徹底的に分析し、どの部分に問題があるか・改善が必要な点は何なのか、情報を元にして洗い出します。これは、物流全体の現状を把握することで、今後の改善に向けた基盤を整備することが目的です。
目標数値・戦略を立てる
次に、現状分析をもとにして、具体的な数値目標を設定し、その達成に向けた戦略を立てます。この段階で、企業全体的な物流戦略や中長期的なビジョン、数値の測定頻度に管理方法なども明確にしておくことが重要です。
ルール設定・社内周知
設定した物流KPIを運用・管理していくために、社内のルールやガイドラインを策定し、全従業員に周知します。ここで重要なのは、従業員がKPIの意義や目的を十分に理解し、日々の業務に反映できるようにすることです。社内のコミュニケーションを通じて、KPI導入のメリットや目標を共有することで、運用開始後のスムーズな実行が期待できます。
運用開始・定期的な見直し
運用が開始された後は、定期的にデータを収集し、物流KPIの達成状況をモニタリングします。運用した結果、必要であれば物流KPIの見直しや再設定を行い、PDCAサイクルを回す継続的な改善を進めましょう。
市場環境や顧客ニーズが変化した場合、物流KPIそのものに問題があることがわかった場合は、随時ルールを変更をするといった柔軟な対応かつ迅速な対応が求められます。
物流KPI設定のポイント

物流KPIを設定する際には、いくつかの重要なポイントがあります。これらのポイントを押さえることで、効果的な物流KPI運用が可能になります。
具体的な数値設定
物流KPIを設定する際には、具体的かつ現実的な数値を目標にすることが大切です。漠然とした「改善」や「効率化」ではなく、具体的に「物流コストを前年比10%削減する」といった数値目標を設定することで、組織全体が同じ方向に向かって努力することができます。
PDCAサイクルの構築
物流KPIの運用にあたっては、PDCAサイクルを導入します。PDCAサイクルとは、業務改善に関するフレームワークで、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Act(改善)の頭文字をとって名付けられています。
このPDCAサイクルを上手く活用して、定期的に改善活動を行う仕組みを整えることが大切です。そうすることで、物流KPIの進捗状況を定期的に確認し、改善すべき点があればすぐに対策を講じることを可能にした流れを構築できます。
荷主との緊密連携
物流業務においては、荷主との連携も非常に重要です。物流KPIを設定する際には、荷主との協力を得ることで、物流KPIの達成率が向上するだけでなく、物流全体のパフォーマンスが大きく改善される可能性があります。
自社でPDCAサイクルが回せるようになれば、荷主を含めたPDCAを回せるようにしましょう。自社で設定したPDCAのノウハウを活かすことができるため、効率良く荷主と連携が取れるようになります。
まとめ

物流KPIを設定・運用することで、企業は物流業務の効率化、コスト削減、サービス品質の向上など、さまざまな効果を期待できます。しかし、設定した物流KPIは設定・運用して終わりというものではなく、PDCAサイクルを回して継続的な確認と改善が必要です。物流KIPを上手く活用して、物流業務の最適化を目指しましょう。


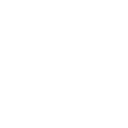 メールフォーム
メールフォーム