COLUMN
WMS(倉庫管理システム)とは?基本機能や混合されやすいシステムとの違いとあわせてメリット・デメリットも解説

毎日運ばれる大量の荷物を、依頼主や指定先へ正確に届ける役割に一役買っているのがWMS(倉庫管理システム)です。
本記事では、倉庫や物流センターで活躍しているWMSに焦点を当てて解説していきます。
基本機能や混合されやすいシステムとの違いとあわせて、メリット・デメリットも解説します。
WMS(倉庫管理システム)とは
WMSとは、Warehouse Management System(倉庫管理システム)の略で、倉庫や物流センター内での作業を効率化することを目的とした、専用管理システムです。
物流における作業の手間やコスト削減など、さまざまな効果が期待できるため、今日の多忙を極める物流業界で注目を集めています。
WMS(倉庫管理システム)の7つの基本機能
の7つの基本機能-1024x576.png)
WMS(倉庫管理システム)には、7つの基本機能が備わっています。
その7つの基本機能によって、物流の倉庫内の作業が効率的にサポートされ、さまざまな効果を生み出しているのです。
以下より、基本機能を見ていきましょう。
1.在庫管理
物流において在庫管理は、生産性の向上や品質管理において非常に重要なポイントです。
その在庫管理を、WMS(倉庫管理システム)では、在庫数をリアルタイムで可視化することができます。
また、ユーザーの需要に見合うよう、適切な補充や出荷も行われるので、受注率の改善やユーザーの満足度を高めることにも繋がります。
2.出荷・入荷管理
企業は、ユーザーへのサービス向上やコスト削減などの競争力を高めることを求めています。
そのニーズに応えるのが、WMS(倉庫管理システム)の出荷・入荷管理機能です。
物流におけるプロセスを適切化し、正確に適切な出荷や入荷が行われます。
3.在庫移動の最適化
倉庫内の在庫移動は、生産性と効率化の向上に欠かせません。
WMS(倉庫管理システム)によって在庫移動をデータ管理することで、作業員は適切なスピードで商品を見つけることが可能です。
在庫移動がWMSによって最適化されることで、生産性と効率化の向上だけでなく、作業員の負担軽減にも繋がります。
4.自動化機能
WMS(倉庫管理システム)は外部の自動化システムとの接続によって、人的ミスの軽減やコスト削減、作業の効率化とクオリティの向上など、さまざまな効果が期待できます。
5.リアルタイムな情報共有
リアルタイムで荷物の情報共有ができるため、関係者はいつでも最新の情報を把握することかできます。
常時作業プロセスの最適化ができるのはもちろん、トラブルが発生した際には、迅速な判断をすることもできるため、解消を最短時間で実現可能に。
また、荷物のリアルタイムな情報を活用することで、企業は競争率の向上をさせることもできます。
6.レポートと分析
レポートと分析機能は、物流倉庫内の効率化やサービス向上のための重要な役割を担います。
WMS(管理システム)は、在庫管理や出荷・入荷管理など、常時さまざまなデーターを記録しているのが特徴です。
データに基づいたレポートを作成することもできるため、向上させたいサービスについての優れた意思決定をサポートします。
他にも、最新のIT技術と組み合わせることで、高度な倉庫管理も実現可能です。
7.進捗管理
労務管理機能では、WMS(倉庫管理システム)によって多くの作業プロセス状況を一目で把握することが可能です。
これにより、倉庫作業者・応答時間・人件費・作業予定・生産性の未達領域などを可視化できるので、企業側はサービス向上や更なる効率化をはかるための対策を投じやすくなります。
時間のコスト削減に大きな役割を果たす機能です。
WMS(倉庫管理システム)提供形態の種類
提供形態の種類-1024x576.png)
WMS(倉庫管理システム)の提供形態は、主にオンプレミス型WMS・クラウド型WMSの
2種類あります。
以下より、それぞれを詳しく解説していきます。
オンプレミス型WMS
オンプレミス型WMSは、自社システムに組み込んでカスタマイズできるタイプです。
自社の要望に合わせた構築が可能なので、必要な機能のみに絞ることもできます。
柔軟な対応ができる分、ソフトウェアのメンテナンスやアップグレードなど、管理を行うITチームの存在が欠かせません。
また、カスタムが可能なことから導入に時間とコストがかかるのも特徴です。
クラウド型WMS
クラウド型WMSは、オンライン上にあるシステムを利用するタイプです。
オンプレス型ほどの柔軟性はありませんが、その分初期費用や導入に時間がかからず、管理も簡単なのが特徴です。
WMS(倉庫管理システム)導入のメリット・デメリット
導入のメリット・デメリット-1024x576.png)
WMS(倉庫管理システム)導入のメリット・デメリットを解説していきます。
導入を検討している際は、メリットだけでなく、デメリットとのバランスを考慮して判断するのがよいでしょう。
メリット
まずは、WMS(倉庫管理システム)のメリットから見ていきます。
1.コスト削減
物流現場の作業は、主に人が行っているため、人件費が物流コストがかさむ要因の内の一つとなっています。
そのため、WMS(倉庫管理システム)を導入して物流プロセスを再構築することにより、従来必要な人数よりも、少ない作業員で運営できる可能性があります。
また、人的ミスを最小限に抑える仕組みが確立できれば、作業員をより活用できるため、これまでかかっていた不要なコスト削減もすることができます。
2.ユーザーと顧客・パートナー企業の満足度向上
WMS(倉庫管理システム)を利用することで、ユーザーはミスの減少や受注処理の効率化、納入の迅速化などの効果が得られます。
荷物の積み下ろし現場では、待ち時間が最短化されることによって、顧客・パートナー企業との関係が改善されるので、ユーザーと顧客・パートナー企業の両方の満足度を向上させることが可能です。
3.現場作業の効率化・ミスの減少
WMS(倉庫管理システム)の端末画面には、作業内容が表示され、作業ミスが発生すると音と端末画面で警告をするなどの機能が搭載されています。
作業員の仕事を適切にサポートしてくれるので、現場作業の効率化・ミスの減少などの期待ができます。
4.在庫の可視化
RFID タグ、センサーなどの位置追跡方法を取り入れると、在庫が入庫からどのようにして動いているのか、リアルタイムで可視化することが可能です。
これにより、正確な需要予測の作成や、ジャストインタイム在庫管理などに役立ちます。
他にも、トレーサビリティの改善効果も期待できるので、リコールが発生した際は、力強い機能になるでしょう。
デメリット
続いて、デメリットを見ていきましょう。
1.導入コストがかかる
WMS(倉庫管理システム)の導入で、倉庫内の作業は効率化されますが、システムの導入にあたって、新たに費用がかかります。
WMSのタイプによっては、導入する際が高額になるものもあれば、月額料金の支払いが必要なものなど、かかる費用はさまざまです。
導入前にしっかりと検討しておいた方がよい部分になります。
2.期待した効果が得られないリスクがある
WMS(倉庫管理システム)には、優秀な機能が備わっています。
全ての機能を上手く利用してこそ、高い業務効率化を得られるものなので、導入する目的と活用方法を明確にしていないと、期待した効果が得られないリスクがあります。
「なんとなく…」や「他の業者が導入しているから…」といった理由で取り入れてしまうと、WMSを上手く使いこなすことが難しくなってしまうため、導入の目的と活用方法をしっかりと考えておきましょう。
混合されやすいシステムとの違い

物流現場で活躍しているのは、WMS(倉庫管理システム)だけではありません。WMSが混合されやすいシステムとの違いを解説していきます。
基幹システムとの違い
基幹システムとは、企業の基幹(財務・生産・販売など)を管理サポートをするシステムです。機能だけでみるとWMS(倉庫管理システム)とよく似ていますが、違いは目的にあります。
基幹システムの目的は、情報を一括管理して企業経営に役立てることです。そのため、倉庫内の在庫は大まかにしか把握することができません。
一方のWMSは、物流倉庫内の効率化をはかることが目的なので、リアルタイムで在庫状況を把握できます。そのため、物流倉庫内を最適化させるには、基幹システムよりもWMSが適しています。
TMSのとの違い
TMS(配送管理システム)は、商品が倉庫から発送され、配達先に届くまでの流れを一括して管理するシステムです。
一方のWMS(倉庫管理システム)は、倉庫内作業や商品管理を行います。
TMSとの違いは、WMSは倉庫内の商品管理を行うのに対して、TMSは倉庫から出た後の商品配送を管理するという部分になります。
WCS・WESとの違い
WCS(Warehouse Control System)は、自動化機器の制御に特化し、効率的な自動化運用を実現します。従来の運用に比べ、人手不足の解消等にも繋がります。
WES(Warehouse Execution System)は、作業状況を可視化し、オペレーションを最適化します。煩雑になりがちなオペレーションの最適化が、経営改善等にも繋がります。
WMSが全体管理を担う一方で、WCSは機器制御、WESは作業の効率化に焦点を当てており、それぞれ異なる側面で倉庫運営を支援します。
WMS導入をする場合の選び方
WMS(倉庫管理システム)を導入するといっても、目的は企業によって異なります。
導入目的を明確にする
導入目的を明確にしておきましょう。
WMS(倉庫管理システム)の機能を、どのように目的を果たす為に活用するのか、検討する必要があります。
目的が不明瞭なまま導入をしてしまうと、WMSを上手く活用することができず、導入の手間とコストだけがかかってしまうことになります。
コストと予算が見合ってる
導入するWMS(倉庫管理システム)によって必要な費用が異なります。また、システムに慣れるまで作業員を教育するコストもかかる場合があるので、予算とWMSの導入コストが見合っているかどうか、しっかりと確認をしましょう。
自社との相性を考慮する
自社との相性も重要です。WMS(倉庫管理システム)を提供する企業の導入例をチェックしてみてください。
どの業界・業種に導入している例が多く実績を残しているのかは、WMSの提供している企業によって異なります。自社の業界・業種と相性のよいWMSを選ぶようにしましょう。
サポートやセキュリティ面が充実している
オンプレミス型なのか、クラウド型なのかなど、導入するWMSのタイプによってどういったサポートが受けられ、セキュリティ面が充実しているかどうかも異なります。
せっかく導入するのであれば、サポートやセキュリティ面が充実している提供企業を選びましょう。
まとめ
インターネットショッピングが普及している今日、WMS(倉庫管理システム)は物流倉庫内を最適化させるシステムとして大いに活躍しています。
しかし、目的を明確にせず導入してしまうと、WMSの機能を生かすことができずに終わってしまうケースもあるので、目的のためにしっかりと活用させるプランを考えた後、導入するようにしましょう。
WMSの機能を上手く活用できれば、コスト削減や生産性の向上など、さまざまなメリットを得ることができます。


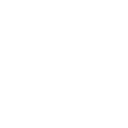 メールフォーム
メールフォーム